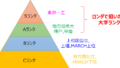はじめに
以前の記事では、学歴ロンダで上位大学を狙う大学生が春休みにするべき勉強内容を説明しました。専門の勉強に関しては上記の内容で十分と思いますが、院試で求められる学力はこれだけではありません。英語(TOEIC)に関しても試験科目に入ることが多いです。全体の1,2割を占めることが多く、ボーダーライン上に居る受験生の合否を最後に決める要素となります。
そこで、本記事では、いわゆる工学系(特に電気情報系)に所属する受験生が院試で合格するために必要なTOEICの点数、勉強法について紹介していきます。
本記事で対象とする大学群
- 旧帝一工+早慶の大学院を目指す受験生
理由に関しては、以前の記事で詳しく解説しています。簡単に言えば、就職面、アカポスへの就きやすさが上記の大学とその他で違うからです。修士で卒業する場合、博士課程へ行く場合、どちらの場合でも選択の幅が広がります。
目標とするTOEICの点数
- 優秀!:800点以上
- 平均。:730点前後
- 微妙…:650点前後
前節で紹介した大学院を外部受験する様々な方々の取得点数を今まで聞いてきましたが、700点前半がボリュームゾーンと言った感じです。内部生基準だと優秀な部類ですが、外部から受ける以上はこれくらいの点数を目指したいです。少なくとも、他の外部生はクリアしていることが多いので、これ以下だと専門科目での巻き返しが必要になります。
逆に、800点以上は少ないです。おそらく、上位1~2割には入れるのではないでしょうか。これだけあれば、英語でアドバンテージを取ることができます。専門科目での些細なケアレスミスは許容できます。
650点を切ると少しまずいですね。地方旧帝大なら内部生の平均点くらいありますが、外部からの受験だとビハインドになります。どんなに英語が苦手でも、是非クリアしたい点数です。
補足
上記はあくまでも一つの目安です。個人的な主観ですが、地方旧帝大寄りの基準かなと思います。日本最高峰の東大を受けるならば、800点でも油断できません。
また、大学によってはTOEFLが必須なところもあります。その場合、いくらTOEICの勉強を頑張ったところで無駄になってしまうこともあります。是非、募集要項をチェックしましょう。
会社に入ってから
院試の場合は相手のレベルもある関係上、700点台がベンチマークになります。一方で、就職してからだと、会社、部署によっては700点でも高いと言われることが多いです。(特にメーカー) (※コンサル、外資は除く)
筆者のTOEICの点数は850点程度ですが、前職(電気設備設計)では部署内で最も点数が高かったです。また、現職(情報系の研究開発)でも上位1割には入っています。
英語の研修へのアサイン、海外転勤のポストが出た時に候補者になることがあります。俺は偉くなって将来稼ぎたいんだ!と言う方は、ここでTOEICをガチっておくと一石二鳥となります。
勉強方法
大方針
TOEICは、大学受験の共通テストと似通っています。リスニングとリーディングで構成される試験形式は勿論、制限時間や大問構成、マーク式など見たことあるようなものばかりです。
院試を受ける学年だと3年以上も前の話になることは承知の上で、当時の自身の勉強方法をリピートすることが最も最善かと思います。国公立を受験したことのある受験生ならば取りつきやすいと思います。
一方で、私大一本だった受験生には厳しいこともあるかもしれません。そこで、筆者としては共通テストの受験経験有無によって、勉強期間を分けることをオススメしています。
- 共通テストの受験経験有り:1カ月
- 受験経験無し:2カ月
勉強スタイル、目標点数によりますが、専門科目の勉強時間も踏まえるとこれくらいになると思います。共通テストの受験経験がある場合は、大学受験である程度の英語を触った人だと考えられます。基本的な単語、文法は身についているはずなので、ガンガン問題演習を積んでいきましょう。単語の勉強は、電車に乗っているときの隙間時間くらいで十分かと思います。
逆に、受験経験が無い場合は基本的な単語を覚えられていないかもしれません。単語帳、文法からの勉強のために余分に1カ月確保しています。(合計2カ月)
ただし、最近のTOEICの出題傾向として、単語、文法の穴埋め問題の数は少なくなってきています。よって、最初の1,2週間で基本事項はすぐに終わらせて、問題演習に移った方が良いと思います。
勉強すると決めた月は、集中的に英語を勉強した方が良いです。毎日1時間は少なく、2時間以上触った方が良いです。1時間だと、昨日勉強した内容の復習で終わってしまい、新しく文章を読む時間が無くなります。とにかく、多読を重視した方が良く、復習と両立するためには2時間必要になる。という理論です。
オススメの参考書
単語帳
金のフレーズをお勧めする方が多いですが、私としては公式の単語帳をオススメします。理由は、試験で出てくる文章により即した形で単語を覚えられるからです。
金のフレーズも、文章の流れで単語を覚えられるようにある程度配慮されています。しかし、文章が短いことが気になります。本番で短文はあまり出てこないです。一方で、公式の単語帳だとある程度の文章の長さになっているため、実際に試験の文章を読んだ時に反応しやすいです。
ただし、覚えている単語の数が少ない。と言う方は、周回重視で金のフレーズに軍配が上がると思います。また、収録単語数も金のフレーズの方が多いです。(しかも、目標点数別で覚えるべき単語も分けられている。)共通テストの受験経験が無い方、基礎勉強を重視する方は金のフレーズにした方が良いかもしれません。
筆者としては、単語を最低限覚えておけば、後は文章の流れで全体を理解する勉強を重視した方が良いと思っています。どれだけ単語勉強を頑張っても、本番で知らない単語が出てくることは付き物です。和訳問題も無いので、ざっくりした理解が出来るなら、英語-日本語の厳密な暗記は不要だと思っています。(900点以上を目指すならば必要かもしれませんが、院試にはオーバースペックだと考えます。)
結論、大学受験で言うと、シス単を金のフレーズ、Duoを公式の単語帳に置き換えるとイメージしやすいです。
文法書
文法特急がオススメです。他サイト様でも良く紹介されています。文法問題の数が少なくなったとはいえ、リーディング全体の3割程度占めています。共通テストではイディオムの出題が多いですが、TOEICでは品詞(動詞、名詞、形容詞など)を区別する出題も多いです。大学受験と毛色が異なりますので、1冊持っておくと吉です。
問題集
演習できる期間を1カ月とすると、3,4冊程度が限度だと思います。筆者としては、易しめ、普通、難しいの三段階の問題集を準備しておき、試験が近づくにつれて難易度を上げていく方式を進めます。
オススメする問題集は、公式問題集と究極の600問です。
公式問題集については、その名の通りです。試験で出てくる形式で勉強できます。問題数が少ない(試験2回分)ですが、効果には代えられないですね。最近の問題集11,10は難しめなので、一桁番台の問題集を先にやった方が良いかもしれません。
究極の600問に関しては、個人的にオススメしています。何より、解説が豊富で、本番に応用できそうな考え方が多く含まれています。3回分のTestがあり、最後のTest3については難しめです。試験前の最終チェック(高地トレーニング)として使用すると良いでしょう。発売から少し年月は経っていますが、色褪せない素晴らしさです。
試験本番時の作戦
結局、勉強してきた時間と英語に対する適正がモノを言いますが、少しでも点数を上げるために筆者が心がけていたことを紹介していきます。
全体としては、10問中3問間違えても7割=700点強確保できます。全部正解することを気負うあまり、今の問題に必要以上に時間をかける必要はありません。カンで答えて良い問題はいくつかある前提で臨みましょう。
リスニング
個人的には、ここで400点取っておきたいです。リーディングは、年を追うごとに分量が増えてきて800点台でも間に合わなかったことが何度かあります。
一方で、リスニングに関しては多少の形式変更は有れど、内容を理解できていれば正解できる問題が多いです。問題集を解いた後はシャドーイングをし、文章を自分のものにしていきましょう。
Part1~4存在し、Part3,4は会話、一つの話者がスピーチをする形式です。ここの出来で、リスニングの成否が決まります。
1つの会話、スピーチに対し各3問出てきます。問題の合間で選択肢の内容を少しだけ確認できる間が有りますが、優先して確認すべき事項は下記です。
下記2項目を問うている問題が存在するか。
- 最優先:選択肢に日付、月、その他特定の選択肢ばかりが挙げられているもの。
- Who is the “名前”など、問われた人の素性を問う問題
上記2点は、ある一文がキーになっていることが多いです。聞き逃してしまうと、カン頼りの選択になってしまいます。問題内容が事前に分かっていると、そこにフォーカスして聞く準備ができます。
一方で、3問中の最初の1問にありがちな、会話をしている場所など全体の概要を聞く問題に関しては、あまり目を通す必要は無いと考えます。会話内容を聞くために神経を尖らせていると、おのずと把握できることが多いからです。2,3問目を中心に見ていった方が良いかもしれません。
リーディング
リスニングの出来次第で進め方を変えた方が良いかもしれません。7,8割できた自信があるなら、400点近くとれる見込みです。リーディングは300点取れば700点なので、6割の正答で良くなります。
文法は、日々の単語の勉強で7,8割程度を目指し、目標点に対し足りない分を文章読解で補完するイメージです。
近年は、最後の文章問題がトリプルパッセージになったり、凄く文章量が多いです。間に合わないことも多いので、目標点数が6割ならそれ以前の問題をしっかり取る。7,8割狙いならスピード重視で解き進めた方が良いと思います。
個人的には、グラフ、メール、チャット(Line)を読み解く問題をオススメしています。文章量が少ないので、解くための時間が他と比べて少ないです。メールの宛先、日時の部分から答えを推測し、マークする問題は頻繁に出てくるので、必ずチェックしましょう。
最後に
悲しい現実ですが、TOEICが出来た所で英語は話せるようにはなりません。本記事では、あくまでもTOEICで高得点を取るための勉強方法を説明してきたに過ぎず、英語が出来るようになる勉強方法ではありません。
ただし、英語を勉強するやる気がある!と周囲にアピールするための”錯覚資産”としては有用です。院試で有利にするための勉強が第一ですが、英語で将来の選択肢を増やす意味でも勉強するとモチベーションになるかもしれません。