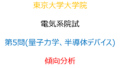はじめに
本記事は、有名大学の院試解答を3年半執筆してきた管理人が作成しています。本日は、東大 情報理工学系研究科院試の一部科目についての傾向と対策方針を紹介します。
東大 情報理工学系研究科 院試の全体
下記の科目で構成されています。試験当日の筆記試験科目は、共通数学と専門科目です。
本記事では、共通数学(線型代数、微分積分、確率統計)について取り上げます。
- 共通数学 (下記3科目 150分)
- 線型代数 ←本記事で紹介
- 微分積分 ←本記事で紹介
- 確率統計 ←本記事で紹介
- 専門科目
- 各専攻に準ずる。(システム情報学、数理情報学、コンピュータ科学、電子情報学)
- 外国語はTOEFLの成績に準ずる。
- 口頭試問も存在するが、本記事では割愛。
各科目の大問は1つだけのため、50分で1題ずつ解く時間配分になります。非常に時間にゆとりがあります。全体的な難易度ですが、中の上くらいの難しさだと思います。一般的な大学の院試で出題される数学の問題に対しては少し難しめですが、全然解けないレベルでは無いくらいの位置です。
個人的には、問題のレベルよりも計算量が多いことが気になります。1題50分のため当たり前かもしれませんが、大問の最初で計算ミスをした時のリスクが大変高いです。安心を買うため、(1)(2)の問題は検算しておいた方が良いでしょう。
科目別の難易度は、線型代数>微分積分≧確率統計と考えます。(年による変動はありますが)
線型代数ですが、像に関する問題が非常に多いです。グラフに関数を図示する作業および一次変換に関する内容が毎年出ると考えて良いでしょう。大学受験ではよく出てきますが、大学院入試としては稀な傾向になります。他の大学でよくある、行列の固有値を求めて対角化すれば完答できる問題が少ないため、このような難易度としています。過去問を用いての対策が必須ですが、慣れてしまえばある程度の点が取れる内容と思います。
微分積分については、オーソドックスな問題です。他大学の院試でも見覚えのあることが多いです。ただし、出題範囲が広いです。積分の問題は勿論、微分方程式や、媒介変数表示(微分)なども出ます。広く浅くの対策が欲しいですね。
確率統計については、漸化式にまつわる問題が多いです。大学受験でも見覚えのある問題で、なんとなく手が付けられる方も多いのでは無いのでしょうか。ただし、大学数学の範囲である確率密度関数が出題される年もあります。総じていえば、問題集や他大学の院試でもよく出題される内容です。
以上より、範囲が限られていて対策もしやすいので高得点を狙うべき大問だと思います。
周りが東大生と言うこともあり、全体的には7割欲しいですね。
共通数学の傾向と対策
全体概要
ここ4年間は、下記の項目が出題されました。
- 2024年:
- 線型代数:直線と媒介変数。領域の図示
- 微分積分:常微分方程式と解の図示
- 確率統計:確率漸化式と解の虚数表示
- 2023年:
- 線型代数:半正定値行列と一次変換
- 微分積分:ガンマ関数と二階微分の関係
- 確率統計:ランダムウォークと相関関数
- 2022年:
- 線型代数:行列の因数分解と二次曲線
- 微分積分:変数変換を用いた常微分方程式の解法
- 確率統計:漸化式と平均値の算出
- 2021年:
- 線型代数:領域の一次変換と面積
- 微分積分:微分の定義と関係式を用いた積分の求値問題
- 確率統計:二次元確率密度関数と期待値
どの大問も最後の問題は難しいです。誘導も丁寧ですが、結局は自身との相性で完答できないこともあると思います。前半~中盤の問題は確実に取ることを目指しましょう。
対策に使える教科書
他大の数学の試験傾向を解説している記事でも同じことを言っていますが、自身がお持ちの教科書をそのまま深めていけば良いと思います。数学は一般教養科目のため、学内の講義では多くのクラスに分かれており教科書も千差万別です。専門科目と違い、これと言った指定教科書が存在しないからです。
本記事では、副読本としていくつか紹介します。東大の生協で販売されている教科書からセレクトしてみました。シラバスのページを確認してみても良いかもしれません。
線形代数
明解 線形代数 木村 達雄 (著), 竹内 光弘 (著), 宮本 雅彦 (著), 森田 純 (著)
他の教科書よりも、写像に関する解説にページを割いているように見えます。第5章~9章まで必読と言えます。説明に関してはこれ以上ないほど充実していますが、問題は少ないので、問題集や過去問で別で演習しましょう。
微分積分
微分積分学 齋藤 正彦 (著)
amazonリンク (※なぜか他の本のようにリンクが貼れないので、直接貼ります。)
線型代数と同じく、基本事項を丁寧に説明しています。第3章~第6章までは確認したいです。演習問題も一応ありますが、院試で高得点を取るには少し足りない。と言った印象のため、問題集は別で持った方が良いです。
微分方程式については、特筆すべき書籍がありませんでした。まだ何も本を持っていない場合は、下記をオススメします。
基礎からの微分方程式 稲岡 毅 (著)
説明の分かりやすさで選んでいますが、上記教科書にこだわる必要はありません。変数分離、同次系、ベルヌーイ型、ロンスキアンなど、微分方程式を解くための常套手段が身に着けられるならば何でも良いです。
確率統計
取り上げる該当の教科書なし。
無いことは無いだろう。と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、大学入試までの経験がモノを言うため、わざわざ教科書を取り上げる必要があるのか?と筆者自身は考えています。出題範囲が限られている都合上、何か本を勧めても、ほんの限られたページしか有益になる情報が得られないと考えています。
学問にコスパの概念は不要かもしれませんが、学生の立場からすると限られたお金の中でやりくりしないといけないです。そのため、特に取り上げることはしません。
下記で紹介する問題集に確率統計に関する問題もありますので、そこで勉強すると良いでしょう。
問題集
詳解と演習大学院入試問題 海老原 円 (著), 太田 雅人 (著)
一題一題のボリュームがあり、東大の試験構成と相性が良いです。線形代数、微分積分(微分方程式含む)、確率統計、全ての分野が収録されているので、問題集を分ける必要がありません。それでいて、他問題集に対しても近年の院試問題の傾向を抑えているのでオススメできます。東大の傾向に合致すると自身が判断した場合は、A問題、B問題までやりましょう。
対策に使える他大学の問題
過去問を最優先でやった方が良いと思いますが、あえて紹介するなら下記です。
- 線型代数:京大(先端数理)
- 微分積分:阪大、九大
- 確率統計:阪大、九大
線型代数ですが、京大(先端数理)の過去問は覗いてみても良いかもしれません。似たような問題がたまに出てきます。2020年の大問4が領域の変換による積分問題などが参考になるかもしれません。
微分積分は、阪大の問題が使えるかもしれません。ガウス積分や、ガンマ関数など、類似の問題が出た年度があります。微分方程式の大問もあるため、同時に対策もできます。
確率統計は、そもそも出題されている大学に限りがあります。阪大と九大が出題されていますが、傾向が異なる問題が多いです。阪大は、2024年のランダムウォーク問題、2020年の感染者を数列で表した問題は確認してみても良いと思います。九大は、、記載はしてみたものの、あっさりし過ぎていてあまり参考にならないと思います。
最後に
外部生は、内部生に対し情報面で不利ですが、共通数学の問題に関してならば何とか対策可能な分類だと思います。上記に示した大学の過去問や問題集で、1問でもこれは!と思った問題があれば演習することをオススメします。