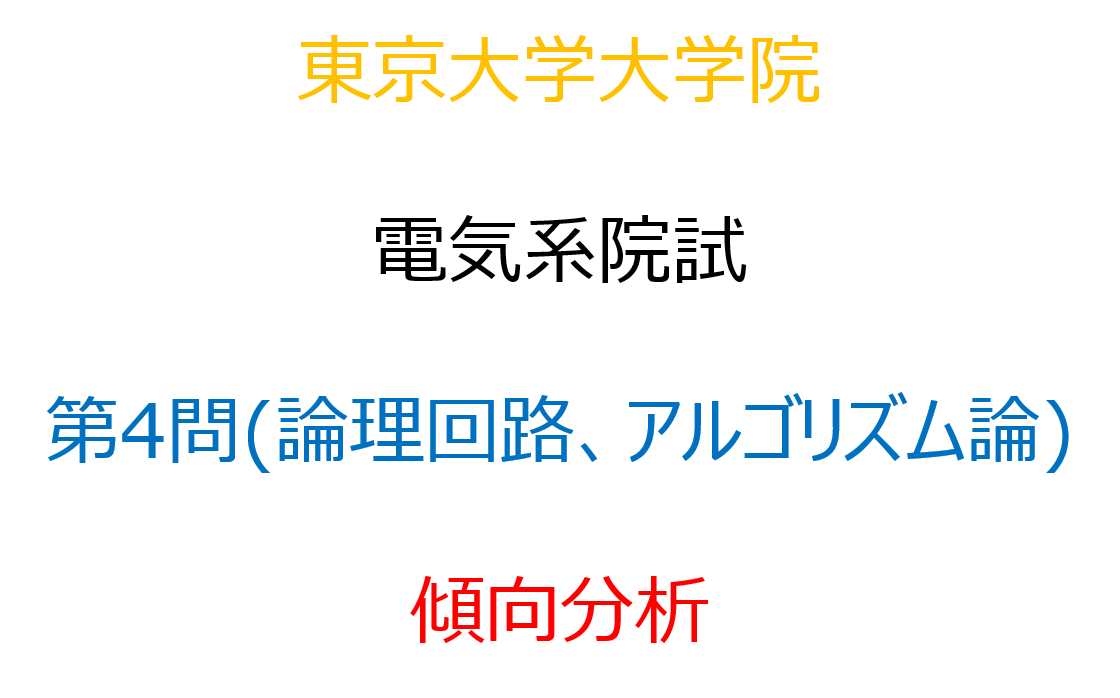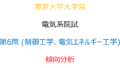はじめに
本記事は、有名大学の院試解答を2年半執筆してきた管理人が作成しています。東大の第4問は、論理回路とアルゴリズム論で構成されています。それぞれの傾向と対策方針を紹介します。
東大 電気系専攻 院試の全体
下記の試験科目6題から2題を選択し、解答します。2題合わせて150分と、時間にゆとりがあります。
その分、一つ一つの分野は他大と比較してしっかり問われます。
- 電磁気学(第1問)
- 電気回路、電子回路(第2問)
- 情報理論、信号処理(第3問)
- 論理回路、アルゴリズム論(第4問) ←本記事で紹介
- 量子力学、半導体デバイス(第5問)
- 制御工学、電気エネルギー工学(第6問)
第4問は、他の分野と比較して初学の学習コスト(時間)があまりかかりません。
プログラミングで疑似コードを記載する問題が出題されるものの、2講義分抑えておけば全範囲網羅できます。
一方で、第1問、第2問は、講義として3~4個分該当するため、範囲が広いです。(その分対策書は豊富にあります。時間があればこちらを選択すると良いかもしれません。)
論理回路の傾向と対策
全体
東大の論理回路は、分量は多いもののオーソドックスな問題が多いです。2進数の数値計算及び順序回路(カウンタ)が出題されることが多いです。
最近4か年は以下の分野の出題がありました。
- 2023年:論理関数と完全系。6進カウンタ。
- 2022年:全加算器を利用した数値A,Bの和を求める問題
- 2021年:数値の大小比較により、大きい方の数値を出力する問題
- 2020年:状態遷移図を用いたJKフリップフロップ順序回路の設計
どれも、情報系の講義を勉強されてきた方ならば馴染みのある分野になります。ただし、分量としては多いため、全体150分のうち40分程度はこちらに使っても仕方ないと考えます。
前半は真理値表、状態遷移表を埋める問題ですので確実にカバーしたいです。6,7割取れれば合格できる院試において、残り1,2問解くことができれば合格ラインに届くはずです。間違い無いよう注意深く埋めましょう。
後半は本格的な問題が出てきます。
bit演算ならば、クリティカルパスなど、計算時間も含めた回路設計を求められます。AND、OR、XORなど、素子ごとに遅延時間が与えられており、初見では戸惑うかもしれません。
ですが、実際の処理としては、論理関数の簡単化と変わりません。
NOTが冗長なものを消す。XORよりもAND,NOT,ORの方が早い場合は、XORをこちらの表記に直して回路設計する。など、定性的に考えると方針が立つ問題が多いです。
学部入試でも、分量多めの即興性重視であることから、院試でもその力を問われているかもしれません。
対策に使える参考書、他大学の問題
論理回路、順序回路の参考書は色々あります。内容自体はオーソドックスであるため、自分の所属する大学のシラバスに載っている参考書で大体対応できそうです。
その上で、筆者が紹介するならば下記になります。
論理回路入門 坂井 修一 (著)
東大の指定教科書です。東大に特化した院試対策を行うならば、選択した方が良いです。
理解を優先したいならば、下記の本がお勧めです。
ビジュアル論理回路入門 井澤 裕司 (著)
題名の通り、読みやすい本です。2進数の変換から順序回路、さらには論理素子に使われる電子デバイスまで幅広く紹介されています。体系的な理解を求めるにふさわしい本です。
他、bit演算に関して、以下の本が詳しく記載しています。
コンピュータハードウェア 富田 眞治 (著), 中島 浩 (著)
絶版となっており、手に入れることが難しいです。ご自身の所属する大学で蔵書されているならば、チェックしてみましょう。
分野ごとの類似問題として、下記の大学が挙げられます。自身の苦手な分野に合わせてチェックすると良いと思います。
- 全加算器を用いた2進数の計算:名大、東北大、電通大
- 比較器の設計:電通大
- カウンタの設計:京工繊
アルゴリズム論の傾向と対策
全体
ここ3年は、2分木探索、ハッシュ法を用いたデータ探索で、平易な問題が続きます。
どの参考書でも説明されている分野のため、取り組みやすいと思います。論理回路と同じく自身が所属する大学の教科書でも事足りると思います。
対策に使える参考書、他大学の問題
その上で、私は以下の本を紹介します。
Cによるアルゴリズムとデータ構造 茨木 俊秀 (著)
京大、東北大講義の指定教科書です。私も使っていましたが、分かりやすいです。プログラムのコードも細かく書いています。しかし、プログラミングに自信が無い方ですと、読み解くのに苦労するかもしれません。
アルゴリズムとデータ構造 (岩波講座 ソフトウェア科学 3) 石畑 清 (著)
東大の講義指定教科書です。東大を専願するならば、購入検討すると良いと思います。ちょっと年度が古いため、書店などで内容を確認された方が良いかもしれません。
- 2分木探索:阪大(電気電子情報通信工学専攻) 電通大
- ハッシュ法:阪大(電気電子情報通信工学専攻)
第4問を選択するデメリット
電磁気、電気回路と比較して学習コストが少なく、ある程度の点が取れるまで早いと思います。しかし、下記の分野が出題されたとき、点数が取りにくいかもしれません。
- 論理回路:論理関数の簡単化
- アルゴリズム論:動的計画法
論理回路は、2016年のように論理関数の簡単化が出題されることがあります。この時は、傾向から外れます。東北大の院試(情報基礎1)が近いので、時間があれば対策すると良いです。
アルゴリズム論は、動的計画法が出題されたときは要注意です。どのような最適化問題が出題されるか分からないからです。計算も複雑で、プログラムを読み解く時間もかかります。
他科目の完成度にもよりますが、この時は別の大問を選択した方が良いかもしれません。
結論
東大 電気系院試 第4問(論理回路、アルゴリズム)は、情報系の科目を勉強してきた方ならばオススメできる科目です。
また、他大を併願するうえで一緒に勉強できる分野ならば選択すると良いと思います。
逆に、電磁気、電気回路、電子回路など、電気系科目をゴリゴリ勉強している受験生ならば見送った方が良いと考えます。(第1問、第2問、+保険の科目で事足りるため)