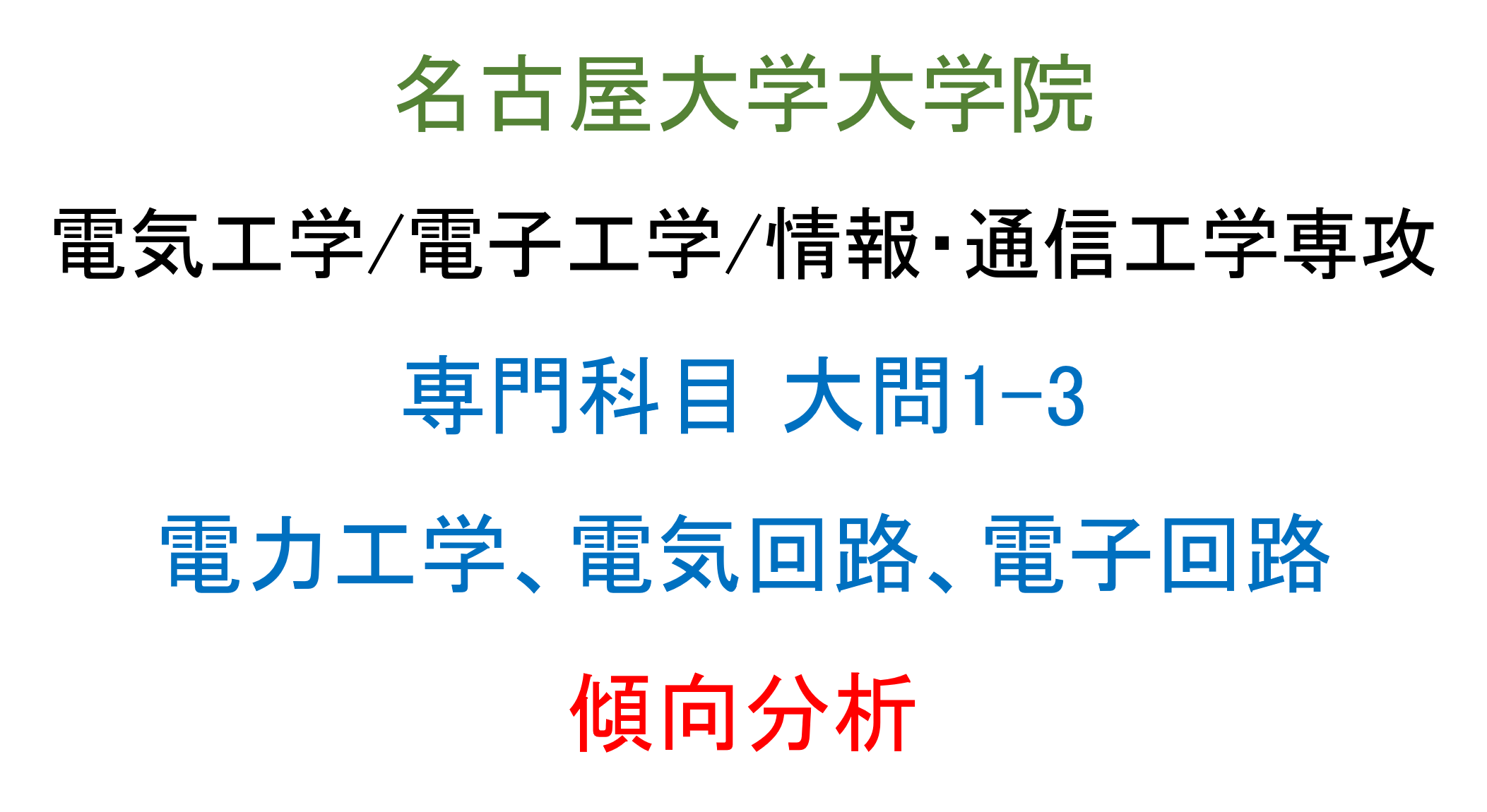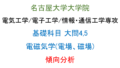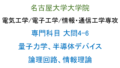専門1-3の科目内容
電力工学、電気回路、電子回路の3題から構成されています。
後者2題については標準的な内容ですが、電力工学については他大学にはあまり無い本格的な内容が出題されます。
名大 電気電子情報通信 院試の全体
基礎科目+専門科目で構成されています。
本記事で紹介する科目は専門科目に属します。志望コース共通で、6題中3題選択することが必要です。そのうち、電気回路、電子回路、論理回路(専門5)から選択できるのは2題までです。残りは、電力工学、量子力学・半導体デバイス、情報理論から選択します。
試験時間は180分で、1題当たり60分の配分になります。大学入試同様、時間に余裕があります。
- 電力工学←本記事で紹介
- 電気回路←本記事で紹介
- 電子回路←本記事で紹介
- 量子力学・半導体デバイス
- 論理回路
- 情報理論
科目制限が設定されているだけあり、難易度としては、電気回路=電子回路<電力工学だと思います。(右に行くほど難しい)
まず、電力工学は電検二種レベルの内容が出題されます。単位法、電力円線図、安定度(ノーズカーブ)など2次試験レベルの内容が出題されます。ゴリゴリの電気系出身者でないと満点を取ることは難しいと思います。
一方で、三相交流の計算など、前半は典型的な問題が出題されます。このパターンを抑えることで、6割程度の得点ならば安定して確保できそうです。
電気回路は、フェーザ回路の計算と過渡現象が良く出題されます。典型的な問題が多いです。ただし、直列共振、並列共振の組み合わせ回路や、鎖交磁束不変の理など、経験・知識が無いと難しい問題もあります。
ラプラス変換で過渡現象の計算を行いづらいことがありますので、微分方程式でも解けるようにした方が良いと考えます。8割程度の得点を目標にすると良いかもしれません。
電子回路は、トランジスタ、MOSFETがよく出題されます。微小信号等価回路を描き、その利得計算、周波数特性を求める問題が多いです。他大学でもよく出題されますので、演習を十分に行うことで満点も狙える内容と思います。
ただし、オペアンプが問われることもありますので、こちらの対策も忘れずに必要です。
対策に使える参考書、問題集
全体
最近3か年は以下の分野の出題がありました。
- 2023年:
- 三相平衡負荷の力率、ベクトル図の作図。別電圧源を接続したときの有効電力の大小関係
- LRC並列回路の共振特性。スイッチを切り替えた時の過渡電流の計算。作図
- バイポーラトランジスタのパラメータ計算。微小信号等価回路の作図と利得の周波数依存性。
- 2022年:
- 三相平衡負荷の相電流、線電流の作図。有効電力の作図。負荷を並列で繋いだ時の力率改善
- 逆向きの電圧源に切り替えた時の過渡電流の計算。時間変化の図示。
- オペアンプの利得計算。コンデンサに流れる過渡電流。
- 2021年:
- 単位法を利用した送電線の無効電力損失の計算。
- LR並列回路のスイッチを切り替えた時の過渡電流の計算。(鎖交磁束不変の理)
- トランスを利用したバイポーラトランジスタの増幅回路。
電気回路の図示問題ばかり目立ちますが、電力工学もスイッチで力率改善したときの回路の状態の変化を説明することがあります。まず、問題を解くことを覚えることも重要ですが、最終的には回路がどのように変化するのかをイメージしながら自分のものにしていくことが重要です。
電子回路は、増幅回路の出題が目立ちます。変圧器やコンデンサを加えて、応用的な問題を最後に問われることがあります。是非教科書を読み込み、事前知識を持ったうえで問題を解きましょう。
電力工学
電力システム工学 大久保 仁 (編集)
名大のシラバスで紹介されています。電験2種を受験するうえでの参考書としてもよく紹介されます。将来、電力系の仕事に従事したいときは、是非購入すると良いです。3~6章が重点対策分野です。
これだけ電力・管理 -計算偏- 改訂新版 重藤貴也 (著), 山田昌平 (著)
電検二種の対策問題集を利用しても良いかもしれません。2次試験の計算問題において、電力円線図などの計算はよく出題されます。
今後の自身のキャリア次第ですが、買っておくと、社会人になったときにも役立つと思います。
電気回路
基礎電気回路 雨宮 好文 (著)
名大のシラバスで紹介されています。コンパクトに纏まっていますので、学習時間少なく対策することができます。三相交流も説明していますので、電力工学も選択される方は是非読んでみると良いです。欠点は、問題のレベルは少し簡単なことと、略解しか無いです。
下記の問題集を併用することで、対策を進めた方が良いと思います。
詳解 電気回路演習(上下) 大下 眞二郎 (著)
上ではフェーザ回路、三相交流の計算。下では、過渡現象の計算問題が収録されています。
電子回路
現代電子回路学(Ⅰ) 雨宮 好文 (著)
名大のシラバスで紹介されています。電気回路と同じ著者なだけあり、コンパクトに内容が固まっています。問題演習については、他大学の院試問題を活用していくと良いです。
対策に使える他大学の問題
電力工学、電気回路、電子回路ともに分野ごとに紹介します。
基本的に、東大と東工大の問題をメインに対策していくと良いです。
- 電力工学:東大、電検二種
- 電気回路:東大、東工大、阪大
- 電子回路:東大、東工大、阪大
電力工学は、他大だと東大の大問6くらいしか同じ分野を出題していません。古典制御との複合での出題のため、名大のように深堀もしていません。電検二種の問題及び教科書の演習問題で対策した方が良いと思います。(一次試験の理論、2次試験の電力管理がオススメです。)
電気回路は、出題内容自体はオーソドックスです。気に入った大学の問題を解くと良いです。電子回路も同様です。
最後に
筆者としては、電子回路を一番オススメします。計算量が少なく、得点安定しやすいからです。180分の試験時間のうち、30分程度で終えることも夢ではありません。
他、論理回路と電気回路の自身がある方を選択することで2題目を確保。保険として電力工学を取っておくと良いと思います。