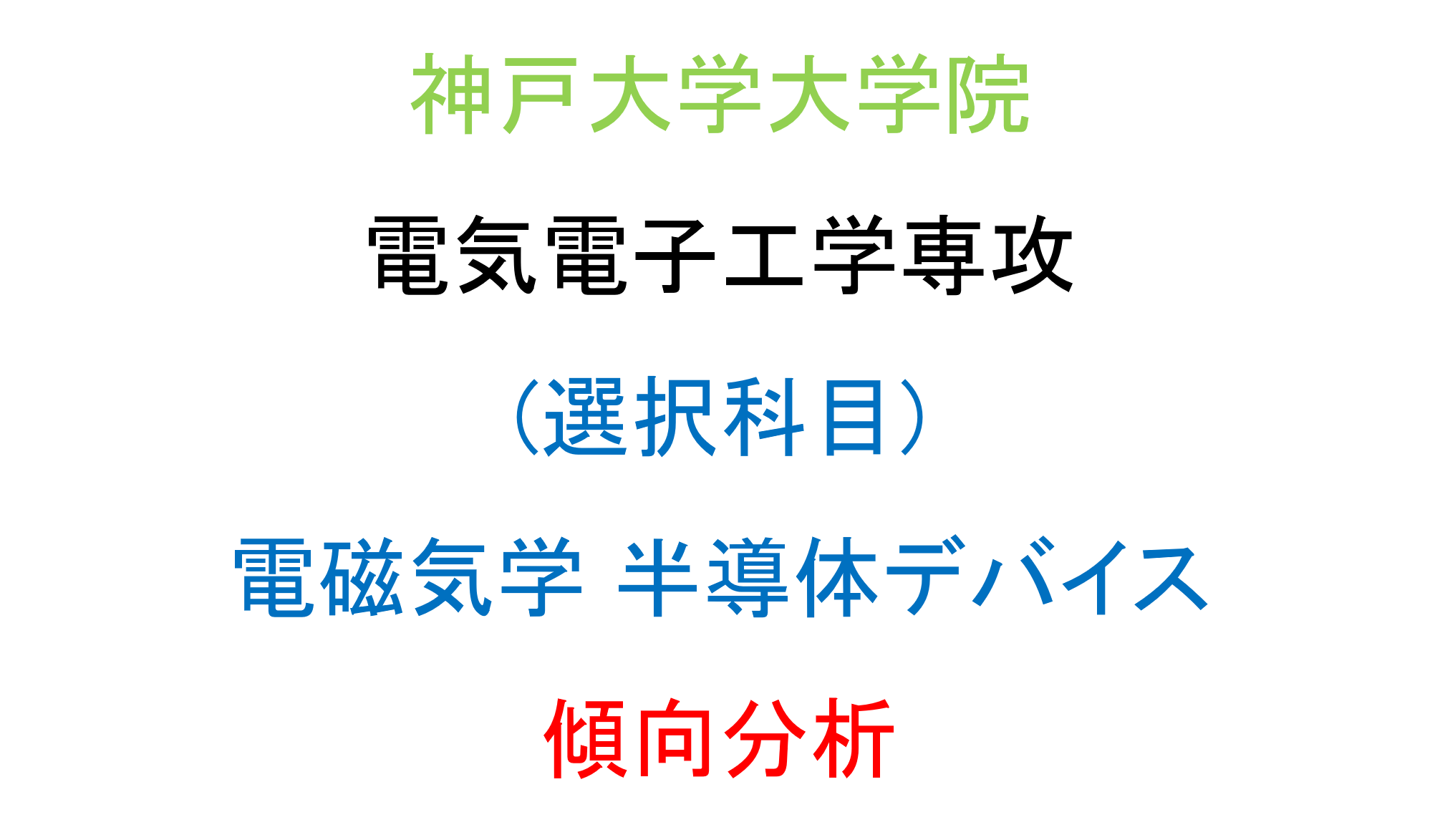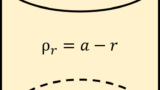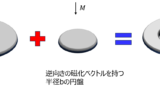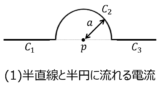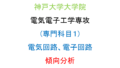電磁気学、半導体デバイスの試験範囲
それぞれ、下記の分野から出題されます。
- 静電界(クーロンの法則、ガウスの法則、鏡像法など)
- 静磁界(ビオサバールの法則、アンペールの法則、電磁誘導など)
- 電磁波(電磁波の伝搬、透過、反射)
- バンド構造、拡散電流
- pn接合
- 金属-半導体接合
- MOSトランジスタの動作原理
電磁気学については、電気回路と同じく具体的な値を代入する問題が多いです。
半導体デバイスについては、今年度から追加された科目のようです。神戸大HPから試験範囲を引用してきました。
範囲だけ見れば、他の大学と同じです。
神戸大 電気電子工学専攻 院試の全体
少し、トリッキーな入試方式になっています。というのも、同じ専攻の中でも受ける研究室によって選択する科目が変わります。
研究室問わず、数学、電気回路、電子回路は必須選択です。
しかし、残りの科目は下記のような選択ルールになっています。
- 数学:
- 線形代数
- 解析学
- 微分方程式
- 微分積分
- 電気回路:(本記事で紹介)
- フェーザ回路
- 二端子対回路
- 電子回路:(本記事で紹介)
- 用語説明問題(CMOS、TTLの特性)
- トランジスタ回路
- オペアンプ
- 選択科目(電子物理系の研究室志望者):下記3科目を全て選択
- 電磁気学(本記事で紹介)
- 量子物性工学
- 半導体デバイス(本記事で紹介)
- 選択科目(電子情報系の研究室志望者):下記4科目の内3科目を選択
- 論理回路
- 情報通信工学
- データ構造とアルゴリズム
- データサイエンス
平たく言えば、電子系の研究室を志望するか、情報系の研究室を志望するかで選択科目が変わるようです。
両方の分野で選択できる科目は無いため、早めに志望研究室について固めておく必要があると思います。
電磁気学について、3つ神戸大の色が出る問題があります。
- クーロンの法則、ガウスの法則からの力のつり合い
- 等電位面の作図
- 電磁波の伝搬
どれも、他大学の院試ではあまり出てくるものではありません。問題集で個別の対策が必要です。
力のつり合いは、ベクトル表記でx,y,z方向に分解する必要があります。いつも、漫然と公式でガウスの法則を当てはめて終わりですが、分解できるよう練習しておきましょう。
等電位面は、\(V=***\)形で考えるか、電場の接線方向を考えることで作図できます。
電磁波の伝搬問題は、教科書レベルではあるものの、出題される大学が限られています。
半導体デバイスについては、本年度から追加になったようです。
どのような問題が好まれて出されるか、まだ分かりません。ただし、範囲で言えば他大学と同等です。また、電子回路の問題で説明問題が多いことから、本分野でも教科書を読んで対策が必要と考えます。
全体
最近3年分は以下の分野の出題がありました。
- 2023年:
- 線電荷から発生する電場。完全導体との関係。
- 異なる媒質に入射する磁場の境界条件
- 2022年:
- 穴の開いた円盤から発生する電場。電位。
- 電磁波の伝搬。ポインティングベクトルの大きさ。
- 2021年:
- 線電荷から発生する電場、等電位面
- ビオサバールの法則を用いた次回の算出。ソレノイドにした時の磁場分布。
※半導体デバイスは出題経験無し。
まず、電場は線電荷で与えられることが多いです。ガウスの法則で、電場分布は求められるものの、極座標表記になっています。よって、x,y平面で分解する練習が必要です。
磁場については、ビオサバールの法則、境界条件が頻出です。特に、境界条件は電磁波でも使うため、必ず覚えておく必要があります。
※電場\(E\)と磁場\(H\)が境界面の接線方向が連続、電束密度\(D\)と磁束密度\(B\)は法線成分が連続です。
役に立ちそうな本サイトの記事
教科書(電磁気学)
神戸大シラバスにて紹介されている本を紹介していきます。
工学系の基礎電磁気学 W.H. ヘイト (著), William H. Hayt (原名), 山中 惣之助 (翻訳), 宇佐美 興一 (翻訳), 岡本 孝太郎 (翻訳) (シラバス対象本)
洋書のため、細かい部分まで説明しています。ただし、演習問題の解答が殆どありません。学問の勉強としては優秀ですが、院試対策と言う点では不向きと言わざるを得ません。
下記の本などで演習した方が良いかもしれません。
新しい電磁気学 太田 昭男 (著)
東北大の元シラバス本でした。少し昔の本になりますが、演習問題の解答が十分に揃っており、神戸大対策に使えます。境界条件の問題や、電磁波まで解説されていることも良いです。
あとは、様々な問題に触れるという意味で下記もオススメします。
詳解電磁気学演習 後藤 憲一 (著), 山崎 修一郎 (編集)
クーロンの法則、線電荷、鏡像法の部分だけでも練習すると良いです。
半導体デバイス
太陽電池のエネルギ-変換効率 喜多 隆 (編集) (シラバス対象本)
「太陽電池」と表題にあることから、効率計算の分野まで紹介しています。半面、バンド構造、pn接合、MOSFETなど、従来の半導体デバイスで紹介している部分の説明が少ないです。
今年度の院試問題次第ですが、参考書で紹介されている下記の本も見ておいた方が良いでしょう。
半導体デバイスの基礎(上)(中)(下) B.L. アンダーソン (著), R.L. アンダーソン (著), 樺沢 宇紀 (翻訳) (シラバス対象本)
上巻はバンド構造、中巻はMOSトランジスタ、下巻は光デバイスなどの応用例を説明しています。
ただ、全て買うには値段が貼ると思います。個人的には中巻を最もオススメします。
半導体関係の研究室に進みたい方は全て揃えても良いかもしれません。
院試対策だけを考えるなら、下記の1冊で済ませても良いかもしれません。
半導体デバイス (series電気・電子・情報系 7) 松波 弘之 (著), 吉本 昌弘 (著)
阪大のシラバス対象本です。薄めのため、半導体デバイスの概要を押さえたい方にお勧めです。
半導体デバイスは最低限の点数で行きたい場合は、これくらいでしのいだ方が良いかもしれません。
対策に使える他大学の問題
電磁気学は、分野ごとに下記の大学がオススメです。
- 電場:東大、京大、東工大、阪大、名大、東北大、九大、北大、電通大、農工大、広島大など
- 磁場:東大、京大、東工大、阪大、名大、東北大、九大、北大、電通大、農工大、広島大など
- 電磁場:東大、東北大、大阪公立大など
電場は、東北大がレベル的に似ていると考えます。線電荷による電場を求める問題が過去に出題されていました。
残念ながら、力のつり合いに関する問題は少ないです。参考程度に覗いてみても良いでしょう。
磁場は、北大がオススメです。円環電流に関する問題が多数出題されています。
電磁場は、東北大が最も傾向が似ています。電磁場の伝搬、反射に関する問題が出題されている年を確認してみましょう。
※半導体デバイスは、2024年度の問題を見てからオススメする大学を判断します。
最後に
神戸大院試の電磁気学は、独特な問題が多いものの、計算量は少なめです。一つ一つの問題を解いての発想を重視していきましょう。